
マイクロアレイとは
 技術的背景 技術的背景
|
| ■遺伝子の機能解析 |
|
遺伝子の機能解析とは、その遺伝子がどういった生命現象に
関わっているかを明らかにすることである。
そのためには、遺伝子がどういったタンパク質をコードし、
そのタンパク質が、どういった場所(組織・器官等)でどういった時期に発現しているか
を明らかにすることが重要である。
遺伝子の発現を調べる方法としては、転写レベルでの発現を調べることが一般的である。以下に、転写レベルでの遺伝子発現解析に用いられてきた方法を列挙する。
マクロアレイ法はナイロンメンブレン等の支持体に遺伝子クローンを固定し、33P等で放射線標識したmRNA(逆転写でcDNA)をハイブリダイズさせ、オートラジオグラフィーで遺伝子発現量を調べる方法である。 |
| ■マイクロアレイの原理 |
|
マイクロアレイの原理そのものはマクロアレイ法と同じである。異なる点は、遺伝子断片(プローブ:探り針)を固定する支持体がメンブレンではなく、ガラス板であること、アレイのサイズが小さく、高密度であること、遺伝子発現を解析する際にハイブリダイズさせるRNA(ターゲット)をアイソトープではなく、蛍光で標識する点である(詳しい解説は、実験の流れへ)。 プローブとして固定する遺伝子数を増やすことにより、より網羅的な遺伝子発現の解析が可能となる。逆に、マクロアレイやマイクロアレイはプローブとして固定された遺伝子以外の遺伝子の発現に関する情報は得られない。 従って、ゲノム的視点にたった網羅的遺伝子発現解析を目標とする場合は、プローブ数が多いに越したことはない。
マイクロアレイには現在、2通りの方法が存在する。
|
| ■GeneChipについて |
|
スポッター等を用いてガラス板に上にDNAを固定するのではなく、フォトリソグラフ法により、ガラス板上で25mer程度のoligoDNAを合成する方法である。1つの遺伝子あたり、塩基配列データから16カ所から20カ所の25merを設定し、25mer完全一致と13塩基目を意図的に違えたone-base mismatchのoligomerセットを組にして、プローブとする。アレイは公表されているデータベースのデータから一度設計すれば、DNAクローンの維持やスポッターなしで、Chipは使うことができる。また、プローブDNAの長さが一定であり、配列が既知なため、ハイブリダイゼーションの強さに影響をあたえるGC含量も一定にすることができるので、発現量の定量的解析には理想的なアレイと考えられている。欠点としては、データベース情報からプローブを作製しているため、興味深いクローンについて解析しようと思ったときに、改めてクローンを単離する必要があることである。
(詳細は、Affymetrix社のHPへ)
|
| ■cDNAマクロアレイについて |
| 我々が現在行っている方法であるが、そもそもはStanford 大学のBrown研究室で開発された方法である。ガラス板にDNAを固定する方法として、キャピラリー状のペンで打ち付ける方法(ペンの形状にも種々ある)、インクジェット方式をとる方法等、いろいろな方法が開発されている。この方法の長所は興味深いクローンが見いだされた際にクローンが手元に存在すること、スポッターさえあればいつでもガラス板の準備が可能なことである。逆に短所はスポッター等のハードウエアがまだ高価なことと、数の多いプローブクローンをスポッティング用に準備しなくてはならないことである。 |
 マイクロアレイでは、何ができるのか マイクロアレイでは、何ができるのか
|
| ■マイクロアレイの可能性 |
|
ゲノム構造解析が行われている生物では、殆どの場合、cDNAクローンの大量解析も行われている。cDNAクローン塩基配列をもとにしたデータベース相同性検索により、一部は既存の遺伝子と相同性が見いだされ機能が推察されたものがあるが、大半は機能未知のままの状態である。これらのクローンについて細胞がどのような状況において遺伝子発現が上昇、あるいは低下するかを少ない回数の実験で調べられる方法がマイクロアレイ法である(遺伝子発現プロファイリングとしてのマイクロアレイ)。また、ゲノム構造解析で得られた大量のcDNAクローンの中から、研究者が興味を持っている生物現象(たとえば環境ストレス応答、組織特異的遺伝子発現)等によって発現の変化する遺伝子を見つけだす方法として使い方もある(遺伝子単離技術としてのマイクロアレイ)。マイクロアレイ法はいわば少ない実験トライアルで、極めて多くの遺伝子発現データを獲得できる方法である。
これまでは、どちらかというと分子生物学的実験手法は遺伝子が単離し易い生命現象に適用されて来た。それに対して、生物現象としては興味深いが、どの遺伝子がどう関与してこういった表現型が現れるのか、アプローチが難しいケース、例えばヘテロシス(雑種強勢)、組織培養における再分化能等の実験系にマイクロアレイ法を適用することにより、分子生物学的研究が進むことも十分考えられる。
|
| ■マイクロアレイは一次スクリーニングである |
| 前項で記述したようにマイクロアレイ技術は1回の実験で膨大な量の遺伝子発現データを得られる画期的な技術である。一方、マイクロアレイ技術は遺伝子単離にも使える。マイクロアレイ実験を行うことによって、細胞の状態変化に対応して発現の変化する遺伝子が多く見つかるはずである。ここで強調したいのは、「マイクロアレイ実験のデータを最終データと見なすことはせずに、多くの遺伝子の中からまず一次スクリーニングとして一群の遺伝子を選択するための手法と見なすべき」ということである。我々もマイクロアレイ実験を行っていて、どうやってデータを標準化するか、異なるガラス板間の値をどう揃えるか、コントロールはどうすればよいか、常に発現量が一定の遺伝子は存在するか等の問題で苦労している。ある程度の標準化はできるが、細胞全体が死に向かっている際などは、一部を除いて多くの遺伝子発現レベルが低下する傾向にあるため、標準化等が非常に難しいケースとなる。こういった問題を個々に考え出すときりがなくなるので、マイクロアレイはあくまで一次スクリーニングと考え、そこで得られた遺伝子個々についてNorthern hybridization法や、RT-PCR法で遺伝子発現を検討するのがベターと考えている。 |
 実験の流れ 実験の流れ
|
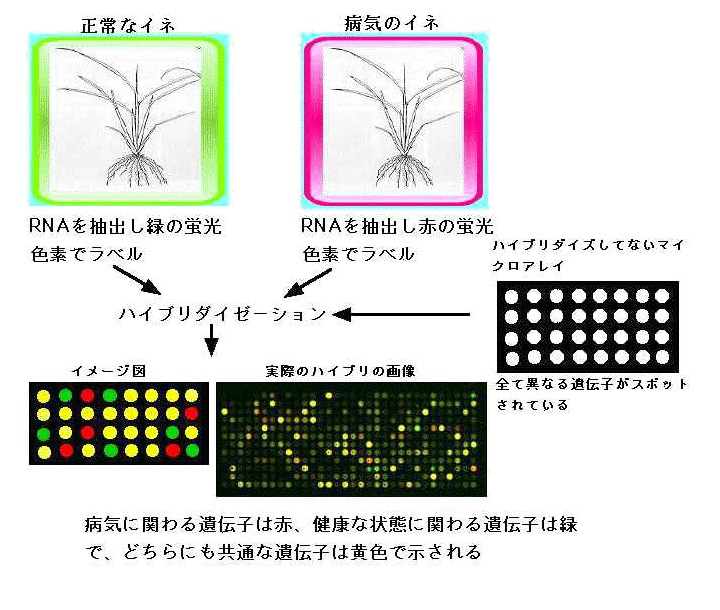
|
 マイクロアレイの問題点と課題 マイクロアレイの問題点と課題
|
|
マイクロアレイは、急激に広まった技術であり歴史が浅いため
いくつかの議論が残されている。その中から次ぎの4点について、説明いたします。
(1)2色法と1色法 |



