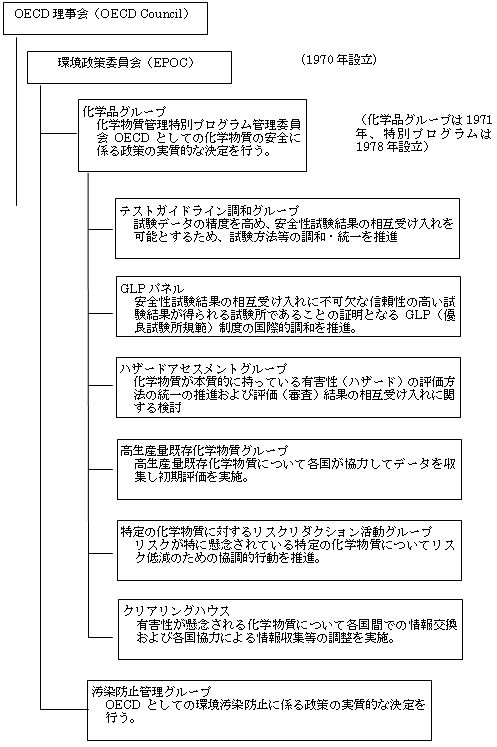前へ | 次へ
第3回ハザードとリスクのコンセプト
ハザードとリスクのコンセプトの違い
石川 安全性評価はリスク・ベースで行われるべきであって、ハザード・ベースで行われるべきでないとよく言われていますが、その辺をお話しいただきたいと思います。
増田
ハザードとリスクというのは、日本語に訳すと両者をあまり区別せず危険性とか有害性とかいって使われていますが、実は全然違うコンセプトなのです。化学物質の世界で言えば、ハザードというのはその物質固有の性質であって、いかなる人為をもってしても変え得ない性質です。例えばAという化学物質は温度が何度になれば引火し、どれだけの量を投与すればどんな生物にどんな毒性が発現するというのは変え得ない固有の性質です。融点や沸点、引火性や爆発性といった物理化学的性状と生分解性、蓄積性、あるいは急性毒性、慢性毒性などはハザードを構成する性質として、全部同じレベルでのデータで示すことができる。その物質がその物質で有る限り変わらない。ハザードというのは科学的に計測された結果そのものなのです。
重要なのは、そういうハザードが存在したからといって危険(リスク)があるとは限らないということです。ハザードに接しない限り(つまりエクスポーズしない限り)危険(リスク)はなにもない。例えば、塩でも砂糖でも固有の特性として毒性を持っている。これらの物質は人間にとって必須の化学物質であるとともに摂取(エクスポーズ)しすぎると害をなす。つまり、エクスポーズの程度によってこれらの物質についての現実のリスクは決まり、益にも害にもなる。リスクというのはハザードとエクスポージャー(暴露)の条件とが加味されて、現実にどの程度危険性があるのかというコンセプトなのです。
そして、ハザードは物質固有の特性であるが故に人の手によって変化させることができないのに対して、エクスポージャーは取扱い方を変えたり、ちょっとした注意を払ったり、いろいろな方法を講ずることによって入の手によって変化させることができる。すなわち、エクスポージャーを制御することによって、リスクは管理することができる。ハザードを知った上でエクスポージャーを分析し、リスクを評価し、そのリスクが受容できるレベルを越える場合には、エクスポージャーを制御してリスク管理をしていくことができる(図1参照)。だから安全性評価はリスク・ベースで行われるべきであり、ハザード・ベースで行われるべきでないのです。リスクとハザードはきちっと分けて認識しなければいけないのに、日本語では一緒くたに議論をしていることが多い。そして、何となく「危険だ、有害だ」というムードで動いてしまう。
炭田
リスク(R)はハザード(H)とエクスポージャー(E)との関数関係にある。つまりR=f(H、E)という形で表されるわけです。OECDの安全性論議で、リスク=ハザード×エクスポージャーという仮想の例を使ってリスクを説明することがよくありました。これは、増田さんの言われたコンセプトの違いを理解する上で分かりやすい表現だと思います。例えば、エクスポージャーをゼロにすれば、ハザードの値に関係なくリスクはゼロとなる。ただし、この式は簡略化し過ぎであって、実際はリスクがエクスポージャーに正比例するわけではありません。
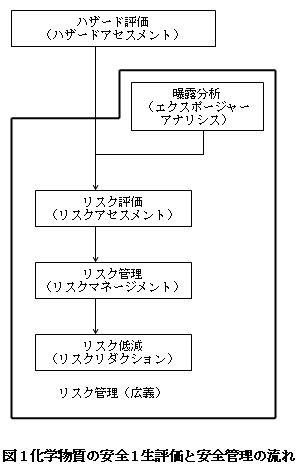 欧米人はリスク評価(Risk
Assessment)という言葉を使うのに対し、日本人は安全性評価(Safety Assessment)という言葉を使います。日本語には、リスク(Risk)、ハザード(Hazard)、デインジャー(Danger)を区別する言葉がなく、これらはすべて”危険”を意味することになるので”安全性”という言葉を使うほうがなじみやすいと感じるのでしょうか。あるいはリスク(危険性)というより、安全性といった方が、聞こえがよいのかもしれません。
欧米人はリスク評価(Risk
Assessment)という言葉を使うのに対し、日本人は安全性評価(Safety Assessment)という言葉を使います。日本語には、リスク(Risk)、ハザード(Hazard)、デインジャー(Danger)を区別する言葉がなく、これらはすべて”危険”を意味することになるので”安全性”という言葉を使うほうがなじみやすいと感じるのでしょうか。あるいはリスク(危険性)というより、安全性といった方が、聞こえがよいのかもしれません。
しかし、言葉のムードで実態が変わるわけではない。一番重要なのは、増田さんの言われたようにハザードを把握した上で、エクスポージャーを制御することによって、リスクを受容できるレベルにマネージしていくというサイエンティフィックな手法の本質を世の中の人々に理解してもらうことだと思います。
増田 リスク評価と安全性評価は同じものを違う方向から言っているようにも見えますが、かなり異なった面もあります。ハザード評価とエクスポージャー分析からリスク評価はできますが、ではどのレベルのリスクなら安全というのか、すなわち、どの程度のリスクなら個人として、社会として受容するのかについては、価値判断という要因が入ってくる。例えば、交通事故については、毎年総入口の1/10000の人が死に、1/150の人が負傷するというリスクを、積極的か否かは別として結果的には日本の社会は受容しており、自動車はこのレベルで安全と考えられているとも言える。受容できるレベルか否かの判断が何らかの理由で変われば、安全か否かの判断も変わる。そして、どのようなものでも必ずリスクがあるから”絶対安全”はあり得ない。このようにリスク評価と安全性評価には異なった面がある。したがって安全性を論じる前に、リスク評価をきちっとしておくことが、より客観的であり普遍的な方法論と言えるでしょう。
炭田
我々は生活のすべての局面で、つまり自動車に乗るときでも、道を歩くときでも、家で台所にいるときでも、生まれたときから常にリスクと正対して生きていて、それを上手にマネージしているからこそ無事生き続けているわけです。バイオテクノロジーの場合もそういう無数のリスクのうちの一つを論じているにすぎないというサイエンス・ベースの相対観を持つことがバイオの安全性の正しい理解につながると思います。
微生物はどのように扱われているか
内田 我々の日常生活は微生物の海の中で生活しているようなもので、生まれたときから我々はそれと知らずに無数の微生物と接して生きてきたのです。微生物は文字どおり小さすぎるので、その存在が肉眼では認められません。見えないものは先ず気味悪い、という第一印象を与えてしまいますから、大変損な立場にあると私は微生物に対して同情してしまいます。我が国では病原細菌学、つまり病気を起こす細菌の学問として微生物学が誕生したことは良くご存知のとおりです。病原細菌学の基礎になったのはいわゆる「コッホの条件」で、これは特定の細菌が特定の疾患の病原体であることを同定するときに踏むべき科学的手順を定式として示したものです。コッホが細菌の純粋培養を基礎とする同定基準を最終的に公表したのは1884年のことでしたが、これが病原細菌学の黄金時代と呼ばれる時代をひらき、以後20年足らずの短期間にコッホの門下生たちを中心に、細菌を病原体とする伝染病の病原がほとんどすべて確定したと言って良いほどの目覚ましい成果が上がりました。この過程で、細菌学者は実に無数の微生物を検査しましたが、病原菌は限られた数しか発見できなかった。大部分の微生物は病原菌ではなかった。
増田
内田先生が言われたように世の中には微生物が満ちあふれており、その中に病原微生物もいるけれども、通常の状態であれば健康な人間が発病する程度に病原微生物にエクスポーズする事はほとんどないから、現実のリスクは少ないわけです。NIHのガイドラインにしても、OECDでの第一ラウンドの議論にしても、まさにエクスポージャーを管理するために「物理的封じ込め」と「生物学的封じ込め」という概念が出てきているわけです。「組換えDNA技術」そのものには特有の危険はないということになると、エクスポージャーを管理し、リスクを管理するための方法は、従来から行われてきた方法・手法で十分で、特別な新しいことを考える必要がないということになる。これが、NIHのガイドラインが改正(緩和)されてきた底流にある考え方であり、OECDでの第一、第二ラウンドの論議の流れの基本的考え方ということになる。振り返って見れば、手を洗う習慣も、煮たり焼いたりして食物をとる習慣も、同じように微生物に対するエクスポージャーを管理し、リスク管理をするために人類が経験的に身につけた重要な方法であるわけです。
内田
私は、たくさんある細菌のうち、ヒトの細菌病原体はごく珍しいことを申し上げたつもりでしたが、その珍しい病原細菌もエクスポージャーを管理すれば病気を起こさないことを増田さんは解説して下さったのですね。さて、外国ではヒトの危険病原体は法律で規制されていますが、日本にはヒトの病原体を規制する法律はなく、あるのは疑似症を含む伝染病患者の発生をシグナルとして発動する「伝染病予防法」によって患者を隔離することです。日本には、いわゆるバイオハザードの規制のためにヒトの病原体を取り締まる法律はないのです。これはちょっと私には分かりにくかったのですが、何しろ明治30年施行になった法律だから、表現が古いのだろうと理解しようとしておりました。しかし、ハザード、エクスポージャー、リスクの考えを適用すれば、案外これは合理的な法体系なのかもしれません。法定伝染病、指定伝染病、疑似症にかかわる病原菌はそれぞれ固有のハザードを有しています。しかし、患者を隔離することによって目に見える形で社会的合意の下にリスクを管理できるのです。病原菌や病気をそれぞれいかに上手にマネージするかは今後も公衆衛生、医療の問題でしょう。
日本でもヒトの病原体のハザード評価が必要な場合がある。基礎医学実験で、病原体をDNA供与体として使うために、病原体自身を培養し取り扱うときには、日本でもやはり外国並みに、ヒトの病原体のハザード評価が必要な場合がでてきます。現在、日本ではこれを「組換えDNA指針」が肩代わりしてその範囲内で引き受ける形式になっています。しかし、「組換え技術そのものに特有の危険性がない」ことが世界的に認められている現在においては、この形式は、「組換えDNA技術が危険である」との間違った考えを社会に固定化する恐れがあります。この制度はそろそろ見直す時期になってきているのではないでしょうか?
石川
この「肩代わり」問題はのちほど再びとりあげてお話しいただきたいですね。次に、化学物質と微生物のハザードとリスク評価のあり方の違いについてお話しいただきたいと思います。
化学物質と微生物の安全性評価のあり方の違い
増田 化学物質ではどんな物質でも基本的にハザードがある。塩でも砂糖でもハザードがあるわけです。砂糖を食ベすぎれば、つまり、ある限界値以上にエクスポーズされれば糖尿病になる。塩も同じで、過剰にエクスポーズするとこれも胃潰瘍や胃がんや高血圧を引き起こし得る。そういう意味では塩も砂糖もハザダス・ケミカル(hazardous
chemicals)です。
さて、OECDの第三ラウンド(1994〜)では環境政策委員会の化学品グループでもバイオの問題をとりあげ始めた。それについて、実は何を懸念しているかと言うと、化学品グループはハザードを有する有害化学物質を伝統的に扱い、それに対してエクスポージャーがあった場合のリスクがどうかという図式でものを論議しているわけです。
しかし内田先生が言われたように、組換えDNA技術そのものは新たに追加されるハザードがゼロであり、かつ大半の微生物にはハザードがないわけです。こういう概念に対して彼らは有害化学物質の経験からいってなじみにくいのです。ハザードが必ずあると思っているからエクスポージャーがあると必ず害があると思ってしまいがちなわけです。
内田 ハザダス・ケミカルと言われているのも、実は十分に微量であれば影響はないし、エクスポージャーとリスクの関係は直線関係ではないということを認識することは重要ですね。繰り返しになりますが、さきほど、炭田さんが、リスクはハザードとエクスポージャーの「関数」である、と言われて、これを単に「掛け算」と言われなかった理由は、「直線的比例関係」ではないことを意識された表現であったのですね。あまり複雑に考えると現実性が薄れるので、単純表現すれば、すべての生物的反応には閾値がある、すなわちあまり小さな作用には反応を示さないと言えます。安全性評価はリスクをベースにすべきで、ハザードをベースとすべきではない。ハザードをベースとすると、いくら微量であっても、危険であるという錯覚に陥る。
炭田 OECDの環境政策委員会では、最近、テストガイドライン(試験方法に関するガィドラィン)、GLP(Good
Laboratory Practice、優良試験所規範)、そしてそれをベースとしたMAD(Mutual Acceptance of
Data、各国の安全性試験データの相互受入れ)など化学物質については成功した安全性評価に関する一連の手法や制度(図2参照)をバイオテクノロジーにも適用しようという委員会を発足させました。生物と化学物質の違いをきちっと認識して本件を取り扱わないと生物に関して適切でない評価や規制をすることになりかねない。
石川
だから環境問題の論議で化学物質を扱うことだけに慣れた人が、バイオに対し間違った扱い方をしないようにするために、バイオをよく分かった人がOECDの環境政策委員会にも出て行って、他の人と十分意見交換をし、知見を広めていく必要があります。
アメリカの環境保護庁(EPA)が属間微生物(つまり組換え微生物)の問題に対してTSCA(Toxic Substances Control
Act、有害化学物質取締法)を準用するということをやっていますね。あれは基本的にミスコンセプトだと思うのです。生物と化学物質には、ハザードの面において大きな違いがあるわけですから。どこでどういうふうに間違ってきたのかを、解明しなくてはいけないと思うのです。
増田
やはりその原因は微生物を化学物質だと言い張って、TSCAで扱ってしまったことにあると思います。「組換えDNA技術には、特有の危険性がない」というコンセプトが確立される前に微生物と化学物質の違いを十分に吟味せずに決めてしまったのではないかと私は思います。病原微生物には当然、ハザードがあるわけです。一方、組換え技術そのものにはハザードがないということがきちっと分かってきたのだから、TSCAで組換え微生物を扱うということは、すなわち、微生物の本来の性質そのものをTSCAで扱うということになる。微生物の固有の特性としてのハザードを化学物質と同じ性質を有するものとして計測するのが本当に正しいのかという議論に行き着くのです。これは、科学的に適切な方法論とは考えにくいと私は思います。
内田
「化学物質等」と書いて組換え微生物を入れる人があるのです。何でも「等」というのを付けるのはお役人の文章によくあります。しかし、この場合は、微生物を化学物質と同じように見ているということを暗示しているのみならず、組換え技術というものに、固有の危険性があるかもしれないと思っていることを示しています。
増田
組換え技術というのは、言ってみればDNAという化学物質を変換するわけですから、すなわち化学反応である。したがって組換え生物は新規化学物質である、というふうな論法でTSCAに入れた。このこと自体無理筋と思いますが、それはさておきその組み換えるという行為、つまり化学反応自身には固有の危険性がないということになったから、結局微生物そのものをTSCAがみていることになる。ということは、微生物そのものも化学物質だという論理で審査する以外のなにものでもなくなるわけです。内田先生が言われたように、日本のある県の指針のたてかたも、微生物に対して有害化学物質の特性と同じような論法をたててやっているわけです。これはどう考えても基本が絶対におかしいと思います。
石川 どこかで必ず矛盾が出てくる。
増田
例えば病原微生物は消毒できるけれども、化学物質は消毒ができない。化学物質をいくら消毒したって、そのハザードはなくならないけれども、病原微生物のハザードは消毒するとなくなる。一方のハザードは消せるのに他の一方は消せないのだから、それらのハザードの評価の仕方が違って当然だと思います。また、別の例として、病原微生物の種特異性があげられます。ある微生物は、ある種の宿主生物には有害だけれどもヒトには有害ではない。その逆のケースも多々ある。こうした種特異性は生物の大きな特徴であり化学物質とは異なっている。これなども両者のハザードの性質の大きな違いです。
これらのことを考えると、化学物質に関するテストガイドライン、GLP、MADなどの手法や制度がどこまでバイオの領域で有効であるかはまだ分かりません。OECDの環境政策委員会はそのところをきちっと論議していくことが必要だと思います。
炭田
有害化学物質と組換え体の安全性を同じレベルでとらえるというおかしな傾向が出てきたのは、欧米政府の組織のあり方にも原因があると思います。例えば、欧州委員会の第11総局(いわゆるDG11)は、有害化学物質と組換えDNA技術をひっくるめて担当しているのです。米国環境保護庁でも有害化学物質と組換え体とを一緒に扱っている。これらの部局では、一般に化学の専門家の数が圧倒的に多く、生物の専門家は小人数なので、彼らは化学物質流の論議に当然影響を受けるでしょう。
日本では化学物質審査規制法で組換え体を扱わないという現状は、実に正しい判断だと思います。この思想を日本の地方自治体でも徹底していただきたいですね。
石川
さて、非常に基本に触れる問題を分かりやすく議論していただきました。これまでのレビューによってハザードとリスクのコンセプトの違いや化学物質と微生物の安全性評価のあり方の違いがはっきりしました。
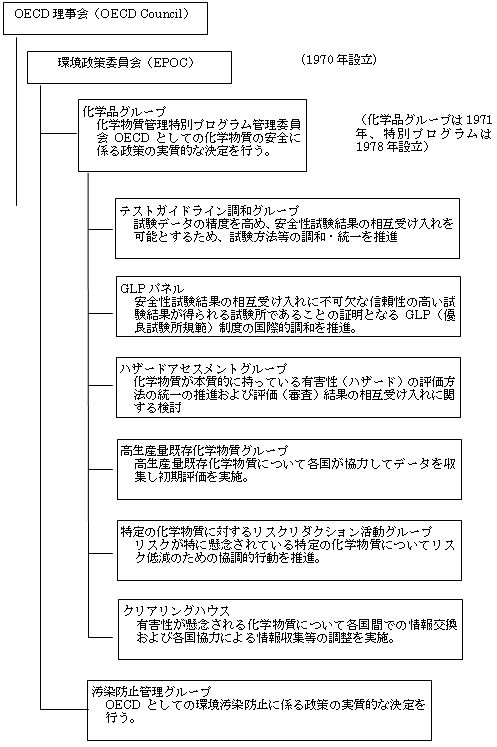
図2 OECEにおける化学物質の安全管理に係る活動
これまでの3回の座談会において、①モラトリアムからOECDまで(1974〜1982)、②OECDでの議論の流れ(1983〜1994)、③ハザードとリスクのコンセプト、をレビューしてきた。これによって、1973年に組換えDNA技術が米国ではじめて開発されてから、1994年に組換えトマトが食品として販売許可されるまでの出来事の背後で、安全性に関する論議が科学者の世界で、そして政策立案者の世界でどのようになされてきたかを大まかに描写できた。
この間の安全性論議の進展は科学的知見の蓄積に裏付けされた安全性に関する種々の概念(コンセプト)の進化、すなわち安全性思想の進化そのものである。これまでの座談会においてこれらコンセプトのいくつかについて大まかに触れたが、次ページの表に示したとおりほかの多くの重要事項にまだ触れていない。
今後の座談会では安全性論議が進展する過程において、新しいコンセプトがどのようにつくられてきたのかについてより詳細に掘り下げてみたい。それによって科学的方法論がどのように安全性論議を先導してきたかがより明確になると考えるからである。主な議論は、多くの科学的知見の蓄積をもつ米国を中心に行われたが、我が国もこの分野における伝統と蓄積した経験の中から重要な一石を投じてきた。これらの論議の過程を追い、それを正確に把握することはバイオの安全性を考えるうえで必須の条件であろう。
これらの安全性コンセプトの変遷という科学的論議の歴史を正史とするならば、機に応じて人々がどのようにこれにかかわり、行動したかという人と社会の歴史を外史と言うこともできよう。正史を縦糸に外史を横糸に織り成すことによって、日本のバイオ政策の軌跡をより深みのある形で生き生きと浮き彫りにすることを目指したい。
(財)バイオインダストリー協会 炭田 精造
表1バイオテクノロジーにおける安全性概念(コンセプト)の進化の概略
| |
|
年
|
組織
|
コンセプト
|
備考
|
|
非意図的放出
|
科学・実験
|
(1973)
|
コーエン&ボイヤー
|
|
組換えDNA技術の登場
|
| 1974 |
全米科学アカデミー/Berg委員会
|
仮想の危険と自主規制
|
モラトリアム(実験の自発的中止)
|
| 1975 |
アシロマ会議
|
生物学的封じ込め
|
組換えDNA技術の安全性に係る論議
|
| 1976 |
NIH
(米国国立衛生研究所)
|
実験ガイドライン
物理的(P1-4)&生物学的(B1-4)封じ込めプロヒビション(禁止事項)
|
自主規制の制度化による実験再開
|
| 1977 |
ファルムス会議(NIH)
|
|
大腸菌K12株が病原菌に変わる可能性は極めて少ない
|
| 1978 |
アスコット会議(US-EMBO)
|
|
ウイルス組換え体の安全性論議
|
| 1978 |
NIH
|
エクセプション(例外指定)
自然界で起きる現象を免除
|
規制緩和開始・改訂手続き明確化
|
| 1981 |
NIH
|
EK系、SC系、BS系実験を免除
毒素のクラス分け
|
|
| 1982 |
NIH
|
禁止条項の削除
|
エグゼンプション(大幅免除)
|
| 1984 |
NIH |
安全性レベル(BL1-4)
宿主ベクター(HV-1、HV-2)
|
|
|
行政・産業
|
(1983)
|
OECD/CSTP/GNE
(科学技術政策委員会
バイオ安全性専門家会合)
|
|
第1ラウンドのバイオ安全性論議開始
|
|
1986
|
OECD/CSTP/GNE
|
GILSP
(優良工業製造規範)
|
安全な産業利用の長い歴史または、生存する事への内在的制約
|
|
意図的放出
|
科学・実験
|
1987
|
全米科学アカデミー
|
組換えDNA技術に特有の危険性はない
|
組換え体の環境導入:何が危険か?
|
|
1989
|
全米科学アカデミー
|
組換え体野外実験の判断の枠組み
|
ファミリアか/管理できるか
/環境影響は?
|
|
行政・産業
|
1986
|
米国連邦政府(BSCC)
|
プロダクト・ベースの原則
|
バイオテクノロジー規制の調和の枠組みの検討開始(プロセスベースからプロダクトベースへ転換)
|
|
(1988)
|
OECD/CSTP/GNE
|
|
第2ラウンドのバイオ安全性論議開始
|
|
1990
|
米国大統領府
|
性能基準の原則
最小負担による安全確保
|
構造基準よりも性能基準を重視
「バイオテクノロジーに対する連邦の監督の原則」および「バイオテクノロジーの規制の基本原則」を提示
|
|
1991
|
米国競争力諮問会議
|
既存の法令体系で十分
|
省庁間の一貫性の欠如を指摘
|
|
1991
|
OECD/CSTP/GNE
|
サブスタンシャル・エクイバレンス(実質的同等)
|
「食品は有意な有害性が追加されない限り安全であるとみなされる」ことに加盟国が原則合意
|
|
1992
|
米国大統領府
|
|
バイオ製品に関する連邦法規の整理を指示
|
|
1992
|
FDA(米国食品医薬品局)
|
バイオ食品に特有の規制をしない
|
判断をするに充分な知識と経験を尊重
|
|
1993
|
OECD/CSTP/GNE
|
実質的同等
ファミリアリティー(親近性)
弾力的運用の原則
|
「ステップ・バイ・ステップ」に拘らない
|
|
USDA(米国農務省)
|
野外試験の規制簡素化
|
6作物につき届出制で十分
|
|
(1994)
|
FDA
|
|
組換えトマトの販売認可
組換えDNA技術の安全性確立
|
前へ | 次へ
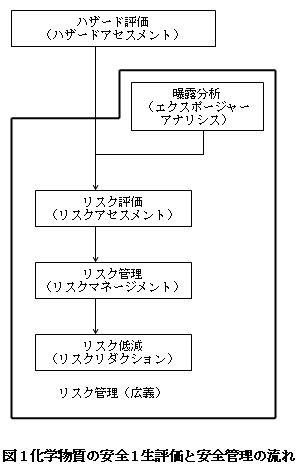 欧米人はリスク評価(Risk
Assessment)という言葉を使うのに対し、日本人は安全性評価(Safety Assessment)という言葉を使います。日本語には、リスク(Risk)、ハザード(Hazard)、デインジャー(Danger)を区別する言葉がなく、これらはすべて”危険”を意味することになるので”安全性”という言葉を使うほうがなじみやすいと感じるのでしょうか。あるいはリスク(危険性)というより、安全性といった方が、聞こえがよいのかもしれません。
欧米人はリスク評価(Risk
Assessment)という言葉を使うのに対し、日本人は安全性評価(Safety Assessment)という言葉を使います。日本語には、リスク(Risk)、ハザード(Hazard)、デインジャー(Danger)を区別する言葉がなく、これらはすべて”危険”を意味することになるので”安全性”という言葉を使うほうがなじみやすいと感じるのでしょうか。あるいはリスク(危険性)というより、安全性といった方が、聞こえがよいのかもしれません。