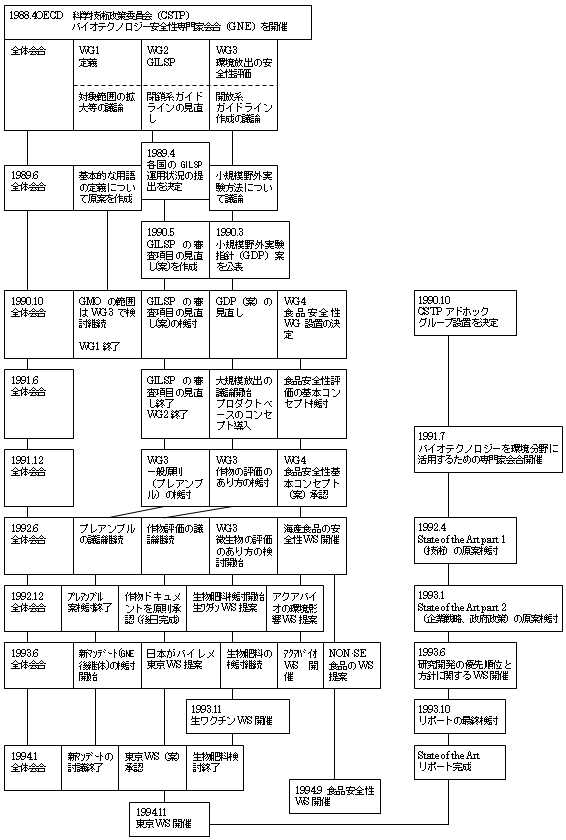前へ | 次へ
第2回OECDでの議論の流れ
石川
組換えDNA技術が研究のツール(tool)として活用され始めた時代における科学の世界での安全性の議論を先月号でお話しいただきました。OECDは科学の世界での議論をふまえて、産業技術として組換えDNA技術を捉えた場合にその安全性をどう考えたらよいかという検討を1983年に開始しました。その第一ラウンドが1983年から86年まであり、GlLSP(優良工業製造規範、Good
Industrial Large-Scale
Practice)のコンセプト(概念)が打ち出されました。そして議論の結果は、1986年に”Recombinant DNA Safety
Considerations”いわゆる”ブルーブック1986”としてまとめられました。日本の場合もそうですが、各国においてもこのブルーブックを関係省庁が産業段階の安全指針のベースにしました。さらに、1988年から94年まで第二ラウンドがあり、プロダクト・ベース(Product-based)のコンセプトが確立され、多くの分野別の安全性論議がされました。今回はこれらの産業段階についての論議の流れを中心にしてお話しいただきたいと思います。
OECD第一ラウンド(1983〜1986)
内田
OECDの第一ラウンドの議論において、組換えDNA技術によってある生物または製品に何がどれだけ付け加わったか、そこに気をつければ、従来の経験がそのまま生きてくるという考えが打ち出されました。安全性の判断の比較対象とすべきことを過去の経験に置いたのです。これがGILSPに体現されているコンセプトです。このコンセプトによってリスク(危険性)の評価ができるということをはっきり宣言したのがOECDの第一ラウンドです。
増田
人類が、長年取扱い経験してきた事象を率直にリスク評価の原点(つまり比較対象)として受け入れたわけです。欧米人にとっては、納豆造りに使われるナットウ菌や味噌、醤油、酒造りに使われるコウジカビは聞き馴れず安心できない。日本人にとって、チーズに生えたかびは同様に気味悪い。しかし、数百年を越える歴史と経験の中で人々は安全性を証明してきたわけです。これを基礎にして産業段階におけるリスク評価とリスク管理ができるということをOECDが世界の専門家、規制当局者等による議論を経て合意したわけです。これがGILSPに体現されている重要なコンセプトです。そして、ある組換え微生物がGILSPの対象にあたるということは、組換えDNA技術によって新たに追加されるリスクはないということですから、歴史的、経験的に長年行われてきた取扱い方法で十分であるということになるわけです。
炭田 第二ラウンドで”実質的同等性”(substantial
equivalence)とか、”ファミリアリティー”(familiarity)というコンセプトが生まれましたが、これらも判断の比較対象とすべき基準を過去の経験においたものです。前者の場合は、食品の安全性を議論するとき、”従来の食品”と比較して実質的に同等かどうかを基準に評価することですし、後者の場合は、生物一般に適用しうるコンセプトですが、例えば作物の環境安全性を議論するとすれば、これまで人類が経験してきた作物育種の歴史などを含む過去の経験や知識をベースに評価するということを意味します。これらのコンセプトの源流は、まさに第一ラウンドのGILSPコンセプトにあったわけです。
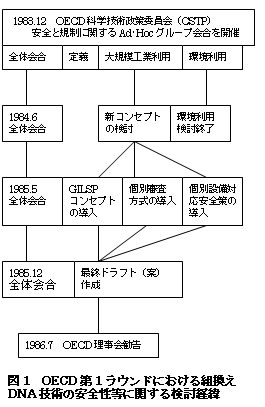 増田
組換えDNA技術をサイエンスの実用化していくことの間には大きなハードルがある。このことは実はバイオだけではなくてあらゆる新しい技術が、それも大きな技術革新のベースとなるような技術であればあるほど、すべて直面する問題であるわけです。研究成果が大学や研究室から工場や社会に技術として出て行くためには、安全性問題のみならず、その他いくつかの大きなハードルを越えなければなりません。特に、安全性問題、さらには安心問題をどう処理できるかによって、新しい技術が世の中で実際に生かされていくか、いかないかさえ左右されることがある。例えば、シングル・セル・プロテイン(SCP、石油タンパク)の例は、やはり技術を社会に出していくための用意、安全性に関する用意がきちっとしていなかった。また社会も安心問題から入ってあまりにも議論のしにくい問題提起をした。その後、SCPは世界で活用されるわけですが、日本では世に出ないまま終わったわけです。
増田
組換えDNA技術をサイエンスの実用化していくことの間には大きなハードルがある。このことは実はバイオだけではなくてあらゆる新しい技術が、それも大きな技術革新のベースとなるような技術であればあるほど、すべて直面する問題であるわけです。研究成果が大学や研究室から工場や社会に技術として出て行くためには、安全性問題のみならず、その他いくつかの大きなハードルを越えなければなりません。特に、安全性問題、さらには安心問題をどう処理できるかによって、新しい技術が世の中で実際に生かされていくか、いかないかさえ左右されることがある。例えば、シングル・セル・プロテイン(SCP、石油タンパク)の例は、やはり技術を社会に出していくための用意、安全性に関する用意がきちっとしていなかった。また社会も安心問題から入ってあまりにも議論のしにくい問題提起をした。その後、SCPは世界で活用されるわけですが、日本では世に出ないまま終わったわけです。
OECDが第一ラウンドの時に出したGILSPというコンセプトは、組換えDNAという新技術を産業化していく過程で、大変優れた価値があった。だから世界各国がそれを取り入れていったわけで、歴史的にも非常に大きな意味があったと思います。これがOECDの議論の中で受け入れられるまでに、かなり議論が揺れたと私は聞いております。しかし、それを受け入れた途端にすっと筋道が整理され、議論が収束していった。そしてGILSPのコンセプトは産業化のための安全性指針の中で重要な位置を占めることとなった。やはり、科学的コンセプトの強さだと思います。
内田
GILSPの論議の出発点になったサイエンティフィックな事実について、その歴史と経験に基づき、かなりの部分を日本が提供しました。そしてGILSPの呼称自身も日本が出したものです。日本の近代発酵工業の発展過程で体験した安全性のポイントはGILSPにみんな入っています。従業員の健康上の管理についてもすでに経験があった。あの”メディカル・サーベイランス”の項目は日本が全部書いている。そのような事ができた理由は、一つは日本の発酵工業が、世界の中で自信を持っていいほどの経験と知見を持っていた。二つ目は、それらをサイエンティフィックに整理された形で持っていたということです。いま国際貢献ということがよく言われるけれども、集大成・体系化された形での知見の提供というのがその第一段階とするなら、それに止まらず、そういう新しいコンセプトの提起をしていくことはさらに大きな貢献であり波及効果も大きい。そういう意味でGILSPのコンセプトを出した日本を私は評価しているわけです。
増田
国際的に採用された制度・仕組みの主要なコンセプトを日本が出した事例というのは、私の知る限りほとんど無い。できればGILSPではなくてJILSPと呼びたい(笑い)。いずれにしても、日本の微生物学の歴史、発酵.工業の経験があったればこそです。現実には、内田先生を筆頭に諸先生方、そして産業界の方々がバイオインダストリー協会に集まり、膨大な作業をしてデータ・資料等をOECDに提供していたわけで、この苦労と努力は大変なものでした。OECDのバイオ安全性論議で、バイオインダストリー協会が果たした役割、そして、それに参画した人々の姿は、歴史に記し残されるべき価値があると思います。バイオという世界で言えば歴史的にはほとんど新参者の通産省あたりが、一定の国際的ポジションを取り、内田先生をはじめ関係の方々からお付き合いいただけるようになったというのも、この時の経験が大きかったと思います。内田先生は、先ほど(先月号)議論させていただいたサイエンスの世界の一連の流れについて、日本国内ではまさに主役として先導し、国際的にも主要なメンバーとして活動してこられました。そういう内田先生とご一緒させていただき、OECDの中に一つの記録を残せたことは、バイオインダストリー協会にとっても通産省にとっても、大変名誉なことだと思います。
OECD第二ラウンド(1988〜1994)
石川
第一ラウンドはこのくらいにしまして、第二ラウンドの一つの特徴は、組換えDNA技術そのものにリスクはなく、安全性の問題はできた製品について考慮すべきであるという、いまでは専門家とか科学者には常識になっているプロダクト・ベースのコンセプトが確立されたことだと思います。そのへんの経緯についてレビューしてみたいと思います。
増田
第二ラウンドの最大の成果は、安全性評価のコンセプトをプロセス・ベース(Process-based;技術ベース)からプロダクト・ベース(製品ベース)へと変えたことです。プロダクト・ベースというコンセプトになったから、食品は食品の領域で、医薬品は医薬品の領域で、作物は作物の領域でそれぞれ考えればよいということになり、その結果それぞれの担当の部局の方々に仕事が回っていったわけですが、まずプロダクト・ベースになるに至った背景が、どういうことであったかということをきちっと認識しておくことが必要です。プロダクト・ベースというコンセプトをその結果だけで捉えると、このコンセプトの持っている本質を捉えそこねて、単に、既存の製品ごとの枠取り意識にお墨付きが与えられたかのようなおかしな理解になってしまうおそれもある。
プロダクト・ベースというコンセプトにどのようにして到達したかというと、またサイエンスの世界の議論が大きな役割を果たした。第一ラウンドは屋内利用の議論でした。第二ラウンドは屋外へ出て、環境中で作物のような組換え生物を利用していく、あるいは組換え技術で作った食品を摂取するといったときの安全性をどう扱うかという議論だったわけです。第一ラウンドの時も実は、「組換え生物を環境中で使うときにはどうしたらいいのか?」ということは議題に上がっていたのですが、サイエンスの上でも知識不足だったし、経験も少なかった。そういうことで第一ラウンドでは結論を出さず棚上げにしたわけです。その後サイエンスの知見が増え、またいろいろな組換え生物を使った野外試験の数も増え、それを製品として開発し世に出す動きも差し迫ってきた。本格的に対処すべき時期が来て、第二ラウンドの議論が始まったわけです。
第二ラウンドにおいて、大きな流れを作ったのは日本とアメリカだったと思います。アメリカでは、サイエンスの世界が動いていた。端的に言うと、全米科学アカデミーが何度かにわたって組換えDNA技術の安全性の問題、とりわけそれを環境中で使う事についてどう考えるべきかという議論をしたわけです。アシロマ会議以降のあらゆる科学的知見を集積し、これに基づき全米科学アカデミーとしての統一的な考え方を作るための議論をしたわけです。その結果、「組換えDNA技術に固有のリスクはない」という結論に至るわけです。
「組換えDNA技術に未知のリスク、固有のリスクはない」ということは、仮に組換えDNA技術を使っても、元のモノが持っているリスクを単純に足し算すればその和がトータルのリスクになるということを意味する。そうなると、食品なら食品、生ワクチンなら生ワクチン、作物なら作物というそれぞれの分野には何百年に及ぶ安全性確保についての経験と体系があるわけですから、それぞれの分野において従来からある安全性の確認方法を基礎として踏襲すれば基本的には必要にして十分だという結論に至るわけです。
実際には、製品(プロダクト)という形で世の中ヘモノが出ていくわけですから、それぞれのプロダクトの安全性に関する従来の確認方法を尊重することこそ、最も確実に安全を確保する方法だということになる。この結論は、技術を社会に出していくためには、大変大きな意味を持っています。
内田 第二ラウンドといえども基本の理念というのは、第一ラウンドの基調がずっと続いている。
増田
組換えDNA技術というのは、始めは医薬の製造を目指した微生物利用が主だったのが、食品、作物、肥料、養殖漁業、環境技術、等々へと、応用範囲がどんどん広がってきました。今まで組換えDNA技術を知らなかった方々がそれを道具として使い出す。
そうするとその方々にとっては、これは新しい技術であり、「新しい技術ということは用心をしないと…」というアシロマ精神が出てきて、そのたびごとに同じことがはじめから繰り返される。
内田 そのたびに新しい人が同じコンセプトを繰り返して学習する。
増田
中央官庁で1980年代に始まった議論は、だんだん外に広がって、今や地方自治体でまた安全性議論が繰り返されるという時代になってきている。場合によっては知らないがための誤解というものも生じて来る。国際的に合意されたコンセプトというものを幾度となく学習し直すことが必要かと思います。
炭田
OECDの中から見ますと、科学技術政策委員会(CSTP)という場を使って、安全性議論を集中的にやって成果を出した。そのうち取り扱う分野が作物とか、肥料とか生ワクチンとか・魚とかどんどん広がっていきますと、安全性専門家会合への出席者が100人を越える規模になります。一方、OECDの中にはいろいろ部局があるわけです。例えば農業局とか、環境局とか・あるいは開発途上国専門の開発センターとか、それぞれの部局がバイオを自分たちの問題として扱いたいということになってくる。OECD事務局の中でも、科学技術産業局からいろいろな部局の方にバイオが必然的に広がっていくということになってきた。
増田
内田先生が先に言われた、アシロマ会議は歴史に残る重要な会議だけれども石橋を叩いても渡らなかったという点で後からみると問題があった、ということは間違いない事実ですが、それをプロダクト・ベースの論議の段階で学問の世界がきちんと清算した。そういう意味で全米科学アカデミーのイニシアチブは大きかったと思います。
内田
その全米科学アカデミーという学界の見解をアメリカ大統領府という行政府がそのまま受け入れたということを私は高く評価します。全米科学アカデミーというのは科学の振興と合衆国連邦政府に対する助言という、二つの役割を持っています。ナショナル・リサーチ・カウンシル(NRC)が、全米科学アカデミーの方針に従ってそれを実行に移す実施機関の性格を持っているのですが、これがよく機能しました。
全米科学アカデミーというのが最初にできて、その次に工学アカデミーというのが分かれて、それからさらに医学部門(インスティチュート・オブ・メディスン)というのに分かれるのですが、その三つを総括して一番上に立っているのが全米科学アカデミーです。しかしお偉い先生方だけだと仕事ができない。仕事をするためにNRCというのが、その三部門の実際の働き手になっている。そういう構造を取っています。
全米科学アカデミーにあたるのが日本学術会議です。私は少々日本学術会議に関係があるのでそういう角度から見てみたのですが、なるほど全米科学アカデミーはうまくできているなと思います。日本の学術会議も大いに発奮し、存在を示していく必要がある。何と言っても、OECDの第一、第二ラウンドでみられるように基本となる科学的原則は、科学の世界の知見から出てくるわけですから。
石川
第一ラウンドでは日本もずいぶん貢献したのですが、第二ラウンドにおきましては、日本はアメリカのよきパートナーであったと言われますが…。
増田
第二ラウンドにおいては、全米科学アカデミーの結論を大統領府が取りあげた流れを最も的確に理解して、アメリカと連携してOECDの場で共通認識として広げていったというのが日本の役割でした。
具体的にはアメリカの考え方を最初に日本が理解して、「それは良いことではないか」と言って彼らに自信を持たせ、そのコンセプトを形あるものへ作り上げるまで議論をしてい
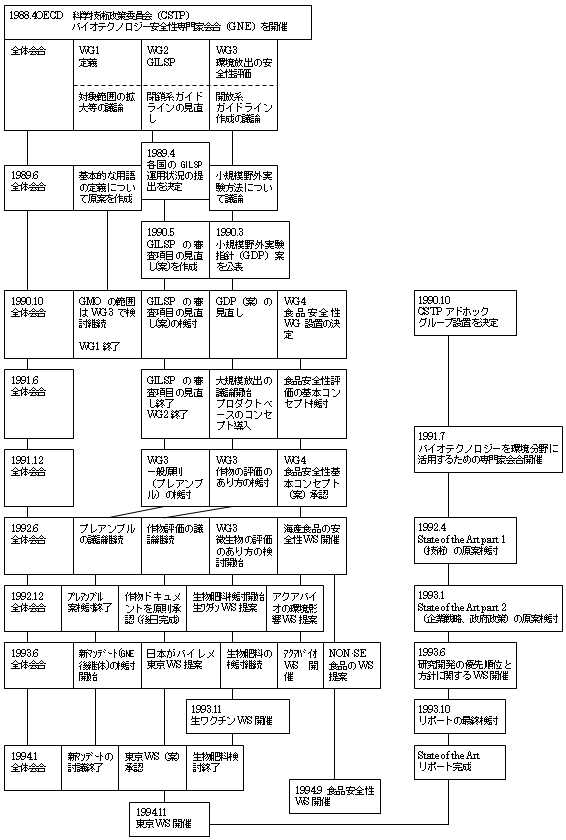
図2 OECD第2ラウンドにおける組換えDNA技術の安全性等に関する検討経緯
ったことが大きかったと思います。あそこで日米間にそういうやりとりがなければ、プロダクト・ベースのコンセプトがOECDで定着したかどうか必ずしも分からなかった。なにしろ、ヨーロッパには、バイオテクノロジーに対して反対の風が非常に強く吹き荒れていましたから。
内田
そのとおりです。コンセプト作りのパートナーであったと思います。これによって第一ラウンドと第二ラウンドの議論の構成が一つにつながった。
炭田
日米がコンセプト作りのパートナーであったということに私も全く同感です。1991年6月に組換え体の環境中での大規模利用の議論をパリのOECD本部で始める直前に・イギリスのマンチェスターで準備会合を行い、日本からは内田先生や増田さんらが出席されました。アメリカが作成したdiscussion
documentをたたき台にして議論が始まったのですが、日本側から「作物は植物界での大腸菌K12株である」という名言が非公式に出されたわけです。つまり大腸菌K12株と同様に、主要作物は人間の手による栽培という保護があるうちは生育できるけれども、自然下に放置すれば雑草との競争に勝ち残って生き続ける力はない、つまり”生物学的に封じ込められている”という意味です。
アメリカ側も大いに触発され、日米双方からGILSPならぬGALSP(Good Agricultural Large Scale
Practice)のコンセプトが生まれた。ヨーロッパ側が、考え方においてあまりにも遅れていたので公式にはOECDのコンセプトとして確立しなかったけれども、その後、このコンセプトは、アメリカ農務省により6種類の主要作物については届け出による簡易手続きを行えばよいとすることで具体化されています。このマンチェスター準備会合は、私にとってはOECD事務局側として出席した第一回目の会議でしたが、それだけに日本側の洞察力の深さに感服しました。構想力という点ではアメリカを越えていたのではないかと思います。惜しむらくは、第二ラウンドでは、日本は提出できるデータを十分持たなかった。
内田 マンチェスターでアメリカが、組換え植物あるいは特定の植物名を挙げず、例えばトマトとは言わずに、作物(Crop
Plant)と言い出したところに私は非常な知性を感じました。さらに従来の作物育種が具体的にはこれだけの性能試験(Performance
test)をしているのだ、とJ.Cook教授が諄々と説明してくれたことを思い出します。GILSPの場合と同様に作物を指定することによって安全な生物種をまとめて処理する方法を提案してくれたのです。OECDが後にまとめた文書ではGALSPのコンセプトの展開が不十分で私は満足ではありません。しかし、この場ではプロダクト・ベースの考え方の確立が急務でありました。
増田
日米連携についてさらに具体的に言えば、日本がJBAを介して二人の人を派遣してOECD事務局を活性化することにより、プロダクト・ベースのコンセプトの展開を、形あるものにしていく主役を果たした事は間違いありません。それから日米財界人会議での経験を足場にして、バイオインダストリー協会(JBA)がアメリカのカウンターパートであるIBA(Industrial
Biotechnology Association)と共にヨーロッパのバイオインダストリーに関与する企業の集まりであるSAGB(Senior
Advisory Group on Biotechnology)に話を持ちかけ、国際バイオインダストリーフォーラム(IBF)という日米欧の連合体を作りました。それによってサイエンス・ベースあるいはプロダクト・ベースの考え方を引っさげて日米欧の産業界がまとまり、OECDやEC委員会にいろんな働きかけをした。これは産業界サイドでの画期的な構想の実現でした。
石川 JBAの代わりに言って下さってありがとうございます。全く同感です。
増田
この時代には、ヨーロッパではOECDの第一ラウンドの議論よりもはるか昔のアシロマ会議時代の議論がまだ行われていて、ドイツでは厳しい規制立法が制定されたりしていた。日本国内でも環境庁がEC委員会の法制化に共感したのか、中央公害対策審議会の中に企画部会を作り、法制化の答申を得るところまでいきました。その時の環境庁のコンセプト自身も「何かあるかもしれない」、「危険かもしれない」、「かもしれないことは規制するのだ」というアシロマ会議的な発想だったわけです。
日本の中での状況は「サイエンス」でいくのか「情念」でいくのかという戦いであったと私は思います。「危険かもしれないのだから規制するのだ」という考え方、さらに言えば「危険か、危険でないかなどはどうでもいい。心配している人がいるのだから法令を作って規制するのだ」というところまで法律系の先生を中心とする方々はおっしゃったわけです。それに対して理系の先生方が言ったのは「危険性があるならば、それに対処する方法があるのだから、その対処する方法に合わせて必要な手だてを打つべきだ。けれども、固有の危険性がないのならば、手を打つ必要がないし、打ったところで意味がない。意味がない事に対して法律を作り、手を打つ必要のないことに手を打つように、法律で義務づけるという事には論理的には矛盾がある」という考え方でした。この二つの主張がぶつかり合ったわけですから、まさに「情念的な発想」と「サイエンスの発想」のぶつかり合いでした。
日本はそういう状況を国内的には比較的早くサイエンス・ベースの議論により論破しつつ、国際舞台ではアメリカとタイアップしてプロダクト・ベース、すなわち「組換えDNA技術に固有のリスクはない」という科学的原則を定着させていった。
石川
科学的な根拠や、蓄積された経験や事実に基づかないで法律を作ると、その運用にはまた大変な無理を生じるということが今までのお話でよく分かります。今に至って欧州委員会やドイツでは法律の改正(緩和)の必要性を論じている。
内田
OECDのブルーブックが出たのが1986年です。通産省の指針が出たのも1986年。デンマークの規制立法が出たのが1986年。ECの指令書が出たのが1990年です。EC諸国ではちょっと世界の動きを見誤ったために、どんどん誤りが誤りを呼ぶ形になって、動きが取れなくなってしまった。EC指令書は手続き論から出たのであって、科学的な根拠があって出たのではないのです。
デンマークの人が、ある時言っていましたけれども、OECDでGILSPという概念が出ているが、それを認識しないうちにデンマークは法律を作ってしまった。えらく、ずれてしまったけれどももう後戻りができなかったと。同じようにEC委員会も、ドイツも法律を作ってしまった。まさにOECDの第二ラウンドの議論がどういう方向へ展開するのかという見通しを誤ってしまったのです。
vそれは情念が強すぎて「とにかく規制するのだ。バイオは悪いのだ」ということにこだわりすぎて心広く、虚心坦懐にものごとの動きを見るのを怠ったがためでした。
増田
OECDの第二ラウンドも1994年で終わりました。アシロマ会議からの科学の流れもここで集大成され、産業段階の議論もここで一応終息した。第二ラウンドの活動が終わったこの時点で改めてOECDの成果を整理してみると、GILSPのコンセプトからプロダクト・ベースのコンセプトヘの流れが「組換えDNA技術に固有のリスクはない」、「各分野の歴史と経験がリスク評価とリスク管理の原点となりうる」という二つの基本原則を確立した。この二つの基本原則の思想は”ブルーブック1993”(Safety
Considerations for Biotechnology; Scale-up of Crop Plants)の第1章”プレアンブル”(Preamble)のセクションにまとめられている。”プレアンブル”は”ブルーブック1986”や”小規模野外実験指針(GDP)1992”の内容を時代の経過と新しい科学的知見をもとに最新のものにするとともに、さらに包括化するものである。この基本原則のもとで、植物や微生物の実験室から大規模野外利用に至る過程については”ファミリアリティー”(familiarity)のコンセプトが確立された。さらに各製品分野の具体例の一つとして食品分野について”実質的同等性”(substantial
equivalence)のコンセプトが確立された。今後これらの原則とコンセプトが各国における安全性評価の基本的な指針となるでしょう。
あとはそれぞれの原則に従って分野ごとにやれば良いという事になった。これによって日本では厚生省、農水省を始めとする所管省庁がそれぞれの分野で実質的に動けるところまできた。アメリカでその後フレーバーセーバートマトなど多くの新製品が実用化されてきている。これはまさに科学的方法論が先導する安全論議の流れの中での成果です。
このように最も基本的なところから論議を積み重ねた結果、プロダクト・ベースというコンセプトを始めいくつかの原則ができたのであって、願わくはプロダクトごとに「俺の権限で…」、「俺の管轄で…」、「ほかの者は勝手にやるな」ということではなくて、根っこを忘れず、基本認識を共有しながら進めていってほしいと期待しています。
内田
OECDでは”マンデート”と呼ばれる事業計画を5年ぐらいを単位に改訂しています。一番最近のマンデートの付図には、シャンデリアのような絵が書いてある。これは加盟国がやりたいことを適切な委員会でとりあげ、そこで分野別の問題を解決していく。そしてまた隣の委員会と協力していくという感じが図に出ています。これはプロダクト・ベースの概念を共生の概念として表しているのですね。
炭田
そのとおりですね。今後OECD内のいろいろな委員会がバイオテクノロジーを取り扱うようになります。これらを調整するために、事務次長を議長とする内部調整グループ(ICGBと呼ばれる)が作られました。加盟国はICGBの動きをみながら、OECD全体として科学的原則をベースとした整合性のある政策が出てくるよう助言する必要があります。特に環境局の化学品グループでバイオの規制について、化学品と似た手法で国際調和を目指すプロジェクトが始まるところです。バイオ関係者は、バイオロジストの立場からきちんとフォローする必要があると思います。
前へ | 次へ
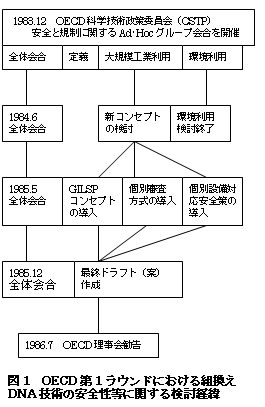 増田
組換えDNA技術をサイエンスの実用化していくことの間には大きなハードルがある。このことは実はバイオだけではなくてあらゆる新しい技術が、それも大きな技術革新のベースとなるような技術であればあるほど、すべて直面する問題であるわけです。研究成果が大学や研究室から工場や社会に技術として出て行くためには、安全性問題のみならず、その他いくつかの大きなハードルを越えなければなりません。特に、安全性問題、さらには安心問題をどう処理できるかによって、新しい技術が世の中で実際に生かされていくか、いかないかさえ左右されることがある。例えば、シングル・セル・プロテイン(SCP、石油タンパク)の例は、やはり技術を社会に出していくための用意、安全性に関する用意がきちっとしていなかった。また社会も安心問題から入ってあまりにも議論のしにくい問題提起をした。その後、SCPは世界で活用されるわけですが、日本では世に出ないまま終わったわけです。
増田
組換えDNA技術をサイエンスの実用化していくことの間には大きなハードルがある。このことは実はバイオだけではなくてあらゆる新しい技術が、それも大きな技術革新のベースとなるような技術であればあるほど、すべて直面する問題であるわけです。研究成果が大学や研究室から工場や社会に技術として出て行くためには、安全性問題のみならず、その他いくつかの大きなハードルを越えなければなりません。特に、安全性問題、さらには安心問題をどう処理できるかによって、新しい技術が世の中で実際に生かされていくか、いかないかさえ左右されることがある。例えば、シングル・セル・プロテイン(SCP、石油タンパク)の例は、やはり技術を社会に出していくための用意、安全性に関する用意がきちっとしていなかった。また社会も安心問題から入ってあまりにも議論のしにくい問題提起をした。その後、SCPは世界で活用されるわけですが、日本では世に出ないまま終わったわけです。